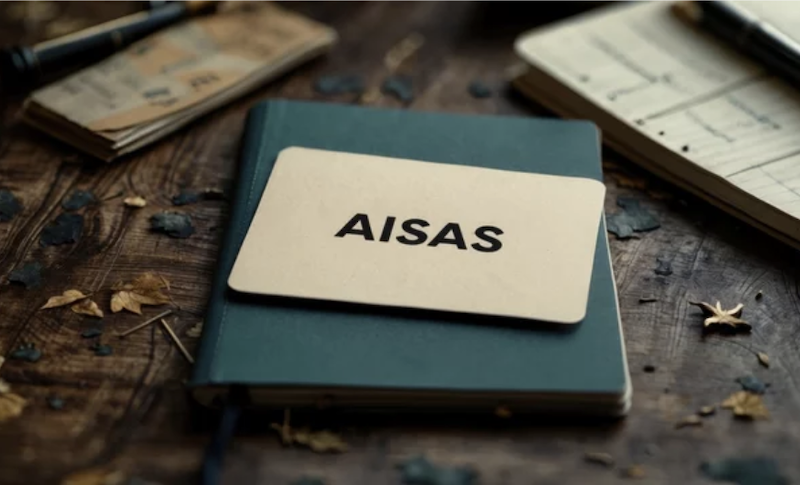| この記事でわかること |
|---|
|
デジタル施策がなぜ成果につながらないのか悩んでいませんか?
そこで今回は、デジタルマーケティングの実績や知識が豊富な株式会社LATRUS(ラトラス)の代表が、デジタルマーケティングで成果を出すために欠かせないAISASの活用法について解説します。
この記事を読めば、AISASの各ステップが実際のデジタル施策にどう役立つのかがわかります。
さらに、購買行動の流れを理解しながら、効果的なマーケティング手法を身につけることができるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
AISASとは
AISASは、消費者の購買行動を5つの段階で表したモデルです。
AISASそれぞれの意味A:Attention(注意)
I:Interest(関心)
S:Search(検索)
A:Action(行動)
S:Share(共有)
デジタル時代に適したこの考え方は、ユーザーの行動や心理の流れを理解し、効果的なマーケティング施策を立案する際に役立ちます。
ここではAISASのそれぞれの意味について解説します。
Attention(注意)
AISASモデルの最初のステップは「Attention(注意)」です。
ここでは、消費者がある商品やサービス、またはブランドの存在に気づくことが起点となります。
従来はテレビCMや雑誌広告が中心でしたが、現在ではSNSやYouTube広告、リスティング広告、インフルエンサー投稿など多様なチャネルが使われています。
消費者が情報の海の中にいる現代では、「目を止めさせること」が非常に困難です。
視覚的インパクトのあるクリエイティブ、ユーザーの悩みに直結するメッセージ設計、表示タイミングなど、細かな工夫が必要です。
特にスマートフォンでは、画面に表示される1秒が勝負と言われるほど、「一瞬の注意」を奪えるかどうかが重要です。
この段階でのKPI(指標)としては、インプレッション数や広告の視認率、スクロール開始位置などが挙げられます。
注意を引けなければ次のステップに進まないため、クリエイティブと設計力が成功の鍵になります。
Interest(関心)
「Interest(関心)」のステップでは、注意を引かれた対象に対して興味を持つかどうかが分かれ道となります。
消費者は「それは自分に関係があるのか」「役に立ちそうか」といった判断を、直感的かつ短時間で行います。
ここでは、興味を深めるためのストーリー性や独自性のあるコンテンツが効果を発揮します。
LP(ランディングページ)の構成では、問題提起から入り、共感やベネフィットを伝え、USP(独自の売り)をわかりやすく示すことが重要です。
また、動画コンテンツやインフォグラフィックの活用も、ユーザーの関心を保ちやすくする方法として有効です。
SNS広告では、「続きを読む」や「タップ」を誘発する見出しの工夫や、短くても印象に残る動画なども注目されています。
興味を引き出せた段階で初めて、ユーザーは自ら行動(検索やクリック)へと移ります。
Search(検索)
AISASにおける最大の特徴がこの「Search(検索)」です。
消費者は関心を持った情報について、さらに詳しく知ろうと自ら検索を行うようになります。
従来の「AIDMA」モデルにはなかったこの行動は、インターネットが普及したことで日常的な行為となりました。
AIDMAとは?消費者が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの心理プロセスを5つの段階に分けて示したマーケティングフレームワークのこと。
この段階では、SEO対策やリスティング広告、口コミ・レビューの管理が極めて重要です。
ユーザーは公式情報だけでなく、他者の評価や体験談も含めて情報を比較・検討します。
そのため、検索結果に表示される自社のページは、信頼性・利便性・網羅性を兼ね備えている必要があります。
また、検索エンジンに加え、SNSやYouTube、最近ではTikTokでのハッシュタグ検索も日常的になっているため、プラットフォームごとに最適化された情報発信が求められます。
検索段階は「自発的な能動行動」であるため、ここでの接点獲得はコンバージョンに直結しやすいポイントです。
Action(行動)
「Action(行動)」は、消費者が実際に商品を購入する、資料請求する、問い合わせを行うなどのアクションを取るフェーズです。
このステップで障壁があると離脱されてしまうため、スムーズな導線と信頼を得る設計が不可欠です。
具体的には、ECサイトであれば購入ボタンの視認性やカート導線の明快さ、入力フォームの簡略化などが重要になります。
また、料金体系や返品保証、FAQなどで安心感を補完することで、ユーザーの意思決定を後押しできます。
BtoBの場合は、ホワイトペーパーのダウンロードや無料相談などを促す形が多く、アクションの種類に応じたLPやCTA(Call To Action)の設計が鍵を握ります。
さらに、行動の直前で再度情報を比較される可能性もあるため、最後までブランドや商品への信頼が持続する工夫も求められます。
Share(共有)
AISASモデルの最後のステップが「Share(共有)」です。
消費者が購入・体験した後に、SNSやレビューサイトなどを通じて情報を発信する行動を指します。
この共有が新たなAttentionを生み、他のユーザーのAISASをスタートさせるという、循環型のマーケティングが特徴です。
企業にとっては、自然発生的なUGC(ユーザー生成コンテンツ)を促す仕掛けが求められます。
たとえば、ハッシュタグキャンペーンやレビュー投稿でのインセンティブ、顧客の声をサイト上で紹介するなど、共有しやすい環境づくりが必要です。
また、ネガティブな口コミや炎上リスクに備えて、ソーシャルリスニングや迅速な対応体制の整備も欠かせません。
共有は企業が完全にコントロールできない部分ですが、だからこそ企業の姿勢や品質が問われ、マーケティングの本質が現れる場とも言えます。
AISASが現代マーケティングで注目される理由
AISASが現代マーケティングで重要視されるのは、ユーザーの行動が「能動的」であることを前提としているからです。
従来のマス広告時代のモデル(AIDMAなど)では、受動的な情報受信と店頭での決断が主な流れでしたが、AISASでは情報収集と意思決定がユーザー主導で進みます。
また、SearchとShareの2ステップが追加されたことで、企業は一度のアプローチで終わるのではなく、検索される価値と共有される魅力の両立を意識する必要があります。
これは、コンテンツマーケティングやSNS施策、SEO、インフルエンサー活用など、デジタル全体を横断した設計に直結します。
とくにZ世代やミレニアル世代では、検索や共有が購買行動の一部として当然のように組み込まれているため、AISASを理解せずにマーケティングを行うことは成果を上げる上での障害となる可能性があります。
現代の消費者心理と接点設計を深く理解する上で、AISASは実践的かつ必須のフレームワークです。
デジタルマーケティングにおけるAISAS活用法
AISASモデルは、デジタルマーケティング施策の設計において非常に有効です。
各ステージに合わせた戦略設計や、ユーザー心理に沿ったコンテンツ提供、複数チャネルを連携させた展開によって、高い成果が期待できます。
ステージごとの戦略設計
AISASの5つのステージ(Attention、Interest、Search、Action、Share)に対応させた戦略設計は、ユーザーの購買心理に寄り添ったマーケティングを実現します。
まず「Attention(注意)」の段階では、短時間で印象を残すバナー広告や動画広告が有効です。
インパクトのあるキャッチコピー、視認性の高いデザイン、ターゲティング精度の高い広告配信が重要です。
「Interest(関心)」では、LP(ランディングページ)や短尺動画でストーリー性を持たせることが効果的です。
ここでは、共感や信頼、ベネフィット訴求がユーザーの関心を深める鍵になります。
「Search(検索)」段階では、SEO対策やリスティング広告の最適化が中心です。
情報の網羅性・信頼性・一次情報の提示が検索上位表示につながります。
「Action(行動)」においては、申し込み導線のわかりやすさ、CVR(コンバージョン率)を高める設計、チャットサポートやLINE対応の導入が有効です。
最後の「Share(共有)」では、ハッシュタグキャンペーンやクチコミ促進、ユーザー投稿のシェアなどUGC(ユーザー生成コンテンツ)を活用する施策が重要です。
このように、各ステージに応じて施策を使い分けることで、ユーザーとの最適な接点を構築しやすくなります。
コンテンツの出し分けと最適化
AISASに基づくマーケティングでは、同じ商品・サービスでもユーザーのステージによって最適なコンテンツが異なります。
そのため、ステージごとにコンテンツを出し分け、最適化する設計が求められます。
たとえば「Attention」では、商品名や詳細を説明する必要はなく、「誰向けなのか」「どんな価値を提供するのか」が一目で伝わるクリエイティブを優先すべきです。
対して「Search」段階では、Q&A、比較表、導入事例、レビューなど、詳細で実用的な情報が重視されます。
また、コンテンツの形式も重要です。
「Interest」ではイメージ訴求に強い動画やカルーセル投稿、「Search」ではブログやホワイトペーパー、「Action」では申し込みフォームやチェックリストPDFなど、目的に応じた選定が必要です。
さらに、ユーザーの属性や流入経路(SNS、検索、広告など)によっても期待する情報は異なるため、パーソナライズやセグメント配信も効果を高める要因となります。
マーケティングオートメーションツールを活用することで、各ユーザーに対して適切なコンテンツを適切なタイミングで届ける仕組みづくりが可能です。
このように、AISASを軸としたコンテンツ戦略は、精緻な設計と運用が求められる一方で、成果への再現性が高いアプローチと言えます。
SEO・SNS・広告の連携強化
AISASの全体最適を目指すうえで、SEO、SNS、広告のチャネルを連携させることは不可欠です。
個別最適な施策にとどまるのではなく、各チャネルがユーザーの異なるステージに作用するよう戦略的に配置する必要があります。
まず「Attention」から「Interest」への導線では、ディスプレイ広告や動画広告を使い、SNSでの拡散力を活かすのが効果的です。
ここでは、リーチ数やクリック率などが評価指標になります。
次に「Search」段階では、SEO対策をベースにオウンドメディアを活用し、信頼できる情報の提供を行います。
リスティング広告で検索結果上位に表示させることで、指名検索以外の流入も獲得可能です。
「Action」では、再訪を促すリターゲティング広告やメールマーケティング、LINE公式アカウントによるセグメント配信などが活躍します。
決済導線や申し込みフォームのA/Bテストも欠かせません。
最後に「Share」を促すために、SNSアカウントとオウンドメディアの連携、レビューキャンペーンの実施、ユーザー投稿の紹介(リポストやストーリーでの活用など)が挙げられます。
以下の表は、AISASステージとチャネル施策の関係をまとめたものです。
| AISASステージ | 主なチャネル | 効果的な施策例 |
|---|---|---|
| Attention | 広告・SNS | 動画広告、バナー広告、インフルエンサー投稿 |
| Search | 検索エンジン・オウンドメディア | SEO記事、比較LP、導入事例コンテンツ |
| Share | SNS・レビューサイト | UGC投稿促進、キャンペーン、リポスト |
このように各チャネルをAISASの各段階に対応させて連携強化することでコンバージョンまでの道筋がスムーズになり、長期的なファン化・リピートにもつながります。
AISASと他フレームワークの違い
AIDMAやAIDCAS、AISCEASといった他のフレームワークとの違いを解説します。
AIDMAやAIDCASとの比較
AIDMA(Attention→Interest→Desire→Memory→Action)は1920年代に提唱された、マスメディア広告時代の消費行動モデルです。
テレビや新聞、ラジオなどで「記憶」に残し、最終的に購買へとつなげる考え方が主流でした。
しかし現代の消費者は、情報を記憶する前に「検索」や「比較」を行うため、AIDMAでは対応しきれなくなっています。
一方、AIDCAS(Attention→Interest→Desire→Conviction→Action→Satisfaction)は、AIDMAに「確信」と「満足」を加えた発展モデルです。
販売員や店舗での接客が購買に影響を与える業態では有効ですが、オンライン完結型の商品・サービスにはマッチしづらい傾向があります。
AISASは、ユーザーが興味を持った商品を検索し、購入後にシェアするというインターネット利用の購買行動を反映しています。
AIDMAやAIDCASでは見られなかった「Search」と「Share」が組み込まれており、現代の情報社会に合致したモデルといえます。
AISCEASとの違いと適用ケース
AISCEAS(Attention→Interest→Search→Comparison→Examination→Action→Share)は、AISASよりもさらに検討プロセスが長い購買行動モデルです。
特に高額商材やBtoB領域で多く採用される傾向があり、比較・検討に多くの時間と情報が必要なケースで有効です。
AISCEASでは、「Search」の後に「Comparison(比較)」と「Examination(検討)」が加わっており、ユーザーがより主体的かつ慎重に選択する姿勢が前提とされています。
これは、自動車、不動産、保険、法人向けソフトウェアなどの分野で非常に適しています。
一方、AISASは比較・検討のステップが明示されておらず、消費者がある程度スピーディに意思決定する行動を想定しています。
たとえば日用品やアパレル、デジタルコンテンツなど、価格が低く比較的直感的に購入されやすい商品にはAISASのほうが適しています。
したがって、どちらのモデルを採用するかは、「商品単価」「購入頻度」「検討期間」「ユーザー属性」などによって柔軟に判断することが重要です。
AISASを使った成功事例と応用例
AISASモデルは、EC、BtoB、SNSを含む多様なマーケティング領域で成果を上げています。
ここでは具体的な事例や応用方法を紹介します。
ECサイトのAISAS型施策例
EC業界では、AISASモデルを活用することでユーザー行動の最適化が進んでいます。
たとえばファッションEC「ZOZOTOWN」では、広告やSNSでの「Attention」を集め、サイト上のトレンド特集やレビュー機能で「Interest」と「Search」を強化しました。
ユーザーは商品詳細ページを見ながら比較・検討し、カートインまでスムーズに誘導される構成になっています。
「Action(購入)」後も、購入商品のレビュー依頼メールやSNSへの投稿促進キャンペーンなどを通じて「Share」を誘導。ユーザーの自然なクチコミが次の見込み顧客の「Attention」と「Interest」につながるという循環が生まれています。
このようにAISASを意識することで、単発のプロモーションに終わらず、持続的な顧客獲得につながる施策が展開されています。
特にリピーター獲得とLTV(顧客生涯価値)の向上に大きく貢献するモデルです。
BtoBマーケでのAISAS応用
BtoBマーケティングにおいても、AISASモデルは有効です。
たとえばSaaS企業では、まず業界課題をテーマにしたホワイトペーパーや事例集を広告で配信し、ターゲット層に「Attention」を喚起します。
「Interest」段階では、導入企業の声や機能比較表などを提供し、製品の関心を高めていきます。
「Search」フェーズでは、自社名や製品名での検索行動を想定し、SEO対策やオウンドメディアを強化しました。
見込み顧客が能動的に情報収集できるよう、資料請求や無料トライアルの導線も設計します。
商談から成約という「Action」の後は、成功事例として紹介したり、顧客の声をウェビナーや記事に活用して「Share」を促進する流れです。
BtoBは意思決定プロセスが長いため、AISCEASなどの拡張モデルも併用されますが、AISASをベースにコミュニケーション設計を行うことで、段階ごとの施策に明確な戦略軸を持たせることが可能です。
SNS時代のShare戦略
AISASにおける「Share(共有)」は、現代のデジタルマーケティングにおいて極めて重要なステップです。
SNSの普及により、消費者の発信力が高まり、企業の広告よりも消費者の投稿の方が購買意思決定に影響を与えることが増えています。
たとえば、スターバックスでは新商品発売時にInstagramやX(旧Twitter)での投稿を促す施策を実施しました。
投稿にオリジナルハッシュタグを設定し、UGC(ユーザー生成コンテンツ)として活用することで、自発的な共有行動を生み出しています。
また、コスメブランドの中には、購入者に「#使ってみた」動画投稿を促し、その中から優れた投稿を公式アカウントで紹介することで、ユーザーとの関係性を深めつつ新たな顧客を獲得している事例もあります。
このように、企業側が「シェアされる前提で設計」するマーケティング戦略は、AISASの「Share」に対応した施策として非常に効果的です。
情報拡散力を持つインフルエンサーとの連携や、レビュー投稿に対するインセンティブ設計なども併用することで、シェアの促進とブランド認知の拡大が実現できます。
AISAS導入時の注意点と改善ポイント
AISASを効果的に導入するには、顧客データの取り扱い、UX設計、そして継続的な改善が不可欠です。
ここでは3つの視点から導入時に意識すべき要点を整理します。
データ収集とプライバシー配慮
AISASモデルでは「Search」や「Action」などユーザーのオンライン行動を把握することが重要ですが、その際に欠かせないのがデータ収集とプライバシーへの配慮です。
クッキーやアクセス解析を通じて取得する情報は、ユーザーの許可を得て透明性を確保する必要があります。
特に近年では、Googleのサードパーティクッキー廃止や、日本の個人情報保護法改正など、プライバシーに関する規制が強化されており、適切な運用が求められます。
企業はプライバシーポリシーの明示、オプトインの導入、匿名化されたデータの活用といった工夫により、ユーザーの信頼を損なうことなくデータ収集を行う必要があります。
また、取得したデータは単に蓄積するのではなく、AISASの各フェーズにおける行動分析に活用することが鍵となります。
顧客体験(UX)の設計
AISASモデルを機能させるうえで、ユーザーが各ステージをスムーズに進めることができる設計、すなわちUX(ユーザー体験)の最適化が不可欠です。
たとえば、「Interest(関心)」から「Search(検索)」に移行させるためには、詳細な製品情報や比較記事への導線を分かりやすく提示する必要があります。
さらに「Action(行動)」を促す段階では、購入ボタンの配置、入力フォームの簡略化、安心できる支払い手段の用意といった要素がUXを左右します。
また、「Share(共有)」に関しては、シェアボタンの配置場所や投稿しやすいUIを設計することで、自然な拡散が期待できます。
これらすべての設計は、AISASの5ステップを念頭に置いた構成でなければなりません。
UXが断絶していると、ユーザーがステージを進まずに離脱してしまうため、常に導線の整合性を見直す姿勢が重要です。
継続的なPDCAサイクルの重要性
AISAS導入後も一度設定した施策をそのまま放置するのではなく、PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)を継続的に回していく必要があります。
ユーザー行動は日々変化し、特にSNSや検索アルゴリズムの変動、競合他社の動きなど外部要因の影響を強く受けるため、定期的な効果検証が欠かせません。
たとえば、「Interest」段階で提供していたコンテンツが以前は反応が良かったとしても、時代の変化に伴い関心を引けなくなる可能性があります。
また「Share」につながる導線が弱い場合は、SNS連携の強化や投稿キャンペーンの導入など新たな施策が必要になるでしょう。
施策ごとにKPIを設定し、どのフェーズでボトルネックが発生しているのかを明確にすることで、AISASモデルの改善精度が高まります。
分析にはGoogleアナリティクスやヒートマップ、ソーシャルリスニングツールなども活用可能です。
データ主導のマーケティング運用が、AISAS導入の成功に直結します。
まとめ
今回の記事では、デジタルマーケティングで用いられるAISASモデルについて解説しました。
成果を出すためには、ユーザーの行動データを正しく分析し、各ステージに合った施策を設計・改善し続けることが重要です。
まずは自社の導線を客観的にチェックしてみましょう。
株式会社LATRUSでは、AISASモデルをはじめとする購買行動理論を活用し、ターゲット分析から導線設計、LINEステップによるCRM構築、LP制作、広告運用、SEO対策まで一貫して支援しています。
「導線を整えて成果を伸ばしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
※ただいまLP等の無料診断実施中