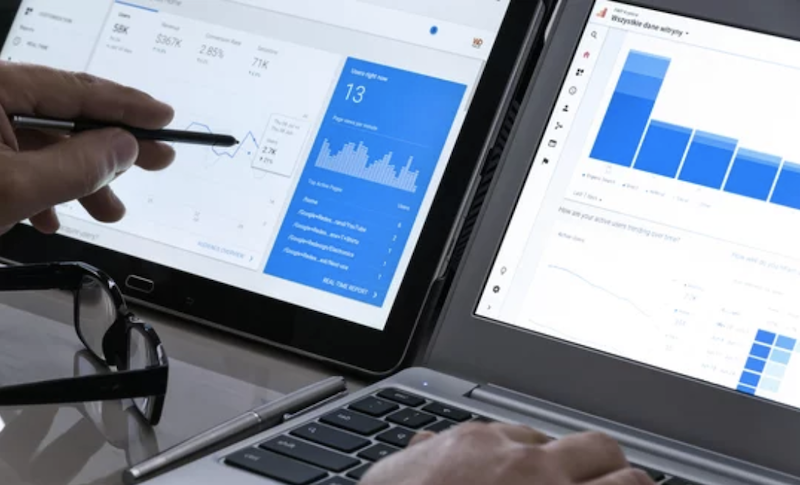| この記事でわかること |
|---|
|
当記事では、SEO対策の実績や知識が豊富な株式会社LATRUS(ラトラス)の代表が、検索ボリュームを活用した効果的なキーワード選定と上位表示につながるSEO戦略について解説します。
この記事を読めば、検索ボリュームの正しい調べ方や最適なボリューム帯の判断基準、さらにロングテールキーワードを使った実践的なSEO対策の手順がわかるので、ぜひ最後まで読んで学んでください。
検索ボリュームとは
検索ボリュームとは、特定のキーワードが一定期間内に検索エンジンでどれだけ検索されたかを示す数値です。
一般的には「月間検索ボリューム(Monthly Search Volume)」という形で表示され、1か月あたりの平均検索回数を意味します。
この数値は、ユーザーの関心やニーズを数量化したものであり、SEOや広告運用の戦略設計において欠かせない基礎データです。
なぜSEO対策において重要なのか
検索ボリュームは、SEO戦略の方向性を決める上でのコンパスのような役割を果たします。
なぜなら、検索ボリュームが高いキーワードは多くのユーザーが興味を持つテーマであり、上位表示されれば大きなアクセス獲得が見込めるからです。
一方で、ボリュームが高いキーワードほど競合も激しく、上位表示までに時間がかかる傾向があります。そこで重要なのが「検索ボリュームの適正な見極め」です。
中程度〜低ボリュームの「ロングテールキーワード」を狙うことで、競合を避けながら安定した流入を得ることが可能になります。
検索ボリュームとユーザー意図の関係
検索ボリュームを分析する際に忘れてはならないのが、ユーザー意図との関係です。
たとえば、検索回数が多いキーワードであっても、情報収集目的の検索が多ければ、コンバージョンにはつながりにくい可能性があります。
逆に、ボリュームが小さくても「購入」「申し込み」「比較」など具体的な行動を示すキーワードは、成約率が高くなる傾向にあります。
このように、検索ボリュームは「数値」だけでなく「検索の背景」に注目して読み解くことが大切です。
検索意図を理解するためには、検索結果ページ(SERP)に表示される上位コンテンツの傾向を分析するのが有効です。
検索ボリュームとユーザー意図を掛け合わせることで、より正確にターゲットを捉えたSEO戦略を設計でき、結果的に検索順位と成果の両方を高めることができます。
無料/有料ツールで検索ボリュームを調べる方法
ツールごとに得られるデータの精度や特徴が異なるため、目的に応じて使い分けることがSEO対策の効率化につながります。
ここでは、検索ボリュームを正確に把握するために活用できる代表的な無料・有料ツールを紹介します。
Googleキーワードプランナーの使い方
Googleキーワードプランナーは、最も基本的かつ信頼性の高い検索ボリューム調査ツールです。
Google広告の管理画面からアクセスでき、アカウントを作成すれば無料でも利用できます。
無料版では「1万〜10万回」といったおおまかな範囲で表示されますが、広告出稿アカウントでは、より具体的な数値データを確認できます。
使い方はシンプルで、「新しいキーワードを見つける」から調べたいキーワードを入力すると、関連語句や検索ボリューム、競合性、入札単価の目安などが一覧で表示されます。
これにより、どのキーワードが需要が高く、どの程度の競合が存在するかを把握できます。
また、検索地域や期間を絞って分析することも可能なため、地域SEOや季節トレンドの把握にも効果的です。
SEO初心者から上級者まで幅広く活用できる基礎ツールといえるでしょう。
Ubersuggest やラッコキーワードなどの代替ツール
Googleキーワードプランナーに加え、無料で使える代替ツールも数多く存在します。
その中でも人気が高いのが「Ubersuggest」と「ラッコキーワード」です。
Ubersuggestは、Googleの検索データを基に独自のアルゴリズムで検索ボリューム・SEO難易度・トラフィック予測などを算出します。
無料プランでも1日に数回の検索が可能で、競合サイトの分析機能も備えています。
特に中小規模サイトの戦略立案に向いており、直感的にデータを把握できるのが特徴です。
一方のラッコキーワードは、関連キーワードを大量に抽出するのに特化したツールです。
検索候補(サジェスト)を網羅的に表示してくれるため、ユーザーがどのような組み合わせで検索しているかを把握できます。
これにより、ロングテールキーワードの発見や記事構成の最適化が容易になります。
これらのツールを組み合わせて利用することで、無料でも実践的なキーワード分析が可能になります。
有料ツール(Ahrefs、Semrush 等)の活用ポイント
本格的にSEOを行う場合は、有料ツールの導入を検討する価値があります。
特に「Ahrefs」や「Semrush」は、世界中のマーケターが愛用する高機能SEOツールとして知られています。
Ahrefsでは、検索ボリュームだけでなくクリック率・被リンク数・キーワード難易度など、総合的なデータを取得できます。
さらに、競合サイトがどのキーワードで上位表示されているかを把握できるため、自社の戦略に落とし込む際の精度が格段に高まります。
Semrushは、検索ボリュームに加えて広告データやSNS分析などの統合機能が充実しており、SEOだけでなくデジタルマーケティング全体を最適化したい企業に向いています。
これらの有料ツールは、月額費用こそ発生しますが、データの信頼性・更新頻度・分析精度が非常に高く、効率的なSEO施策を行う上で強力なサポートとなります。
中長期的な視点で見ると、投資以上のリターンが見込める有用なツール群といえるでしょう。
複合キーワード × 検索ボリュームでSEO戦略を立てる
ここでは、複合キーワードと検索ボリュームを組み合わせてSEO戦略を立てる方法について解説します。
ロングテールキーワードとは?
ロングテールキーワードとは、2語以上の複合語で構成される検索回数の少ないキーワードを指します。
たとえば「SEO 検索ボリューム 調べ方」や「ブログ キーワード 選び方」などが該当します。
これらは月間検索ボリュームが100〜1,000回程度と比較的少ない一方で、検索意図が明確であることが特徴です。
ロングテールキーワードを狙う最大のメリットは、競合が少なく上位表示しやすい点にあります。
大手サイトがカバーしきれないニッチな領域を攻めることで、少ないアクセスでも高いコンバージョン率を実現できます。
また、ロングテール戦略は中長期的なSEOにも効果的です。
複数のロングテール記事を積み上げることで、ドメイン全体の評価が高まり、結果的にミドルワードやビッグワードでも上位表示されやすくなります。
検索ボリュームの目安を把握し、段階的に戦略を構築することが重要です。
ミドルワード vs ビッグワードの使い分け
SEOにおけるキーワード選定では、ミドルワードとビッグワードの違いを理解することが欠かせません。
ビッグワードとは「SEO」「マーケティング」など1語、もしくは非常に検索ボリュームの大きいキーワード(1万回以上)を指します。
一方でミドルワードは「SEO 対策」「キーワード 選定」といった中規模の検索回数(1,000〜10,000回程度)の複合キーワードです。
ビッグワードは確かにアクセス潜在力が高いですが、競合が非常に多く、上位表示までに時間がかかります。
対してミドルワードは、ある程度の検索需要を維持しつつ、競合が比較的少ないため、成果を出しやすいバランス型キーワードといえます。
理想的な戦略は、ロングテールで基礎流入を確保しながら、徐々にミドルワードを狙い、最終的にビッグワードでも勝てるドメインを育てていくことです。
目的に応じてこれらを明確に使い分けることで、無駄のないSEO施策が実現します。
成長段階別に狙うべきボリューム帯
SEO戦略は、サイトや事業の成長段階によって狙うべき検索ボリューム帯が変わります。
立ち上げ初期は、ドメイン評価が低いため、月間100〜500回程度のロングテールキーワードを中心に記事を量産することが有効です。
これにより、検索エンジンに専門性と継続性をアピールできます。
中期段階では、ある程度の評価が蓄積しているため、1,000〜5,000回規模のミドルワードを狙うことで、アクセス数とブランド認知を同時に拡大できます。
このフェーズでは、内部リンク構造を整え、ロングテール記事との関連性を高めることがポイントです。
そして成熟期には、10,000回以上のビッグワードをターゲットに据え、全体のSEOポテンシャルを最大化します。
この段階では、外部被リンクや高品質コンテンツによるドメイン強化が求められます。
このように、成長段階に合わせて検索ボリュームを段階的に引き上げていくことで、無理なくSEOの成果を積み上げることができます。
検索ボリュームをもとにキーワードを選定する方法
SEOの成果はキーワード選定の精度で大きく変わるため、論理的な手順を踏んで戦略的に決めていくことが重要です。
ここでは、検索ボリュームを軸に効果的なキーワードを選定するための5つのステップを解説します。
サイトの方向性とミッション設定
まず最初に行うべきは、サイト全体の方向性とミッションを明確にすることです。
どのようなユーザーに価値を提供し、どんな悩みを解決するのかを定義しない限り、キーワード選定はぶれてしまいます。
たとえば「SEOの知識を提供するメディア」であれば、教育・情報提供を軸に据え、「実践的に使えるSEOノウハウをわかりやすく伝える」など、目的を具体化します。
この段階で明確なミッションが設定されていれば、キーワードの方向性も自然と定まります。
また、ミッション設定はユーザーの検索意図を正確に捉えるための基礎でもあります。
ビジネスゴールとユーザーのニーズを一致させることで、検索ボリュームだけにとらわれない「成果につながるキーワード選定」が可能になります。
キーワード候補を洗い出す方法
次に行うのが、キーワード候補の洗い出しです。
この段階では、ツールを活用して可能な限り多くの候補を集めることが目的となります。
Googleキーワードプランナー、ラッコキーワード、Ubersuggestなどを使い、「SEO」「検索ボリューム」といった軸から関連語や複合語を抽出していきます。
特にラッコキーワードは、ユーザーが実際に入力している検索語句(サジェスト)を一覧化してくれるため、リアルなニーズを把握するのに最適です。
さらに、競合サイトが上位表示しているキーワードも分析対象に含めると、自社が狙うべきテーマの方向性が見えてきます。
洗い出しの段階では「多すぎる」と感じるくらいリストアップして構いません。
後の工程で絞り込むことで、効率的に有望なキーワードを選定できます。
検索ボリューム・競合・意図で絞る
キーワード候補を集めたら、次は「検索ボリューム」「競合性」「ユーザー意図」の3軸で精査します。
検索ボリュームが高いキーワードはアクセス潜在力がある一方、競合も多く上位表示が難しい傾向にあります。
そのため、SEO初心者や新規サイトでは中・小規模の検索ボリューム(100〜3,000回程度)のキーワードを中心に狙うのが現実的です。
加えて、検索意図を正確に読み取ることが重要です。
単にボリュームが大きいだけでは意味がなく、「情報を知りたい」「比較したい」「購入したい」など、ユーザーの目的に沿った内容を提供できるかどうかを確認しましょう。
ツール上の数値だけでなく、実際に検索結果(SERP)をチェックし、上位記事の構成やトピックを分析することで、より精度の高いキーワード選定が可能になります。
優先順位の付け方と記事執筆への落とし込み
最終ステップでは、抽出したキーワードに優先順位を付け、実際の記事構成に落とし込みます。
ポイントは、「成果につながるキーワード」から順に対策することです。
検索ボリュームが小さくても、商品購入やサービス申し込みなどの行動に直結するキーワードを優先的に扱うべきです。
優先順位を決める際は、以下の3つを意識します。
- 検索意図が明確であるか
- 自社の専門領域と一致しているか
- 現時点のサイト評価で上位表示が狙えるか
これらを考慮した上で、記事テーマや構成案を作成します。
たとえば、関連性の高いキーワード同士をまとめて1記事にすることで、内部リンクの最適化やSEO評価の一元化にもつながります。
このように、戦略的に優先順位を付けて執筆することで、SEO効果を最大化し、安定的な検索流入を得ることができます。
注意点とSEO評価を上げるための工夫
長期的なSEO成功には、単に「数値の大きさ」だけを追いかけるのではなく、トレンドの変化やサイト構造の最適化までを視野に入れることが欠かせません。
ここでは、検索ボリュームを基準にキーワード選定を行う際の注意点と、SEO全体の評価を高めるための工夫について解説します。
検索ボリュームだけを追うリスク
検索ボリュームが大きいキーワードは一見すると魅力的ですが、それだけで戦略を立てるのは危険です。
まず、検索数が多いほど競合サイトが強力である傾向があり、上位表示を獲得するまでに膨大な時間とコストがかかる場合があります。
また、ボリュームが多くてもコンバージョン率が低いキーワードでは、アクセスが増えても成果に結びつきません。
さらに、検索意図が曖昧なキーワードでは、ユーザーが求める情報と記事内容がずれやすく、直帰率の上昇や滞在時間の低下を招きます。
検索エンジンはユーザー満足度を重視しているため、結果的にSEO評価が下がる可能性もあります。
したがって、ボリュームだけでなく「検索意図」「競合レベル」「コンバージョンの質」を合わせて判断することが重要です。
季節性・トレンド変動を加味する
検索ボリュームは常に一定ではなく、季節や社会的な動向によって大きく変動します。
たとえば、「確定申告」「ボーナス 投資」などは特定の時期に急増し、それ以外の期間は検索数が落ち込む典型的な例です。
こうした季節性キーワードを把握せずに戦略を立てると、アクセスが予想外に減少するリスクがあります。
このような変動を見極めるには、「Googleトレンド」や「キーワードプランナーの過去データ」を活用し、年間推移を確認することが有効です。
また、トレンド系キーワードを狙う際は、競合が少ない早い段階で記事を仕込む“先取り戦略”が効果的です。
季節性・トレンドを意識したコンテンツ設計を行うことで、ピーク時に効率的に流入を獲得できます。
内部リンク・まとめ記事による構造強化
SEO評価を高めるうえで、サイト内の構造設計も欠かせません。
特に「内部リンク」と「まとめ記事」は、検索エンジンにとって重要な評価要素です。
関連性の高い記事同士を内部リンクでつなぐことで、クローラビリティ(巡回しやすさ)が向上し、サイト全体の評価が底上げされます。
また、特定のテーマを包括的にまとめた「ハブ記事(まとめ記事)」を設けることで、個別記事のSEO効果を集約できます。
たとえば、「SEOキーワード選定」というハブ記事を中心に、「検索ボリューム調査」「ロングテール戦略」「ツールの使い方」などを内部リンクで結ぶ構造を作ると、検索エンジンがテーマの専門性をより高く評価します。
内部リンク設計と記事階層の最適化を意識することで、単発のキーワード施策だけでなく、サイト全体でのSEO強化が実現します。
まとめ
今回の記事では、SEOの検索ボリュームについて解説しました。
検索ボリュームを把握することは、効果的なキーワード選定の第一歩です。
適切なボリューム帯を狙うことで、無駄な競争を避けつつ、確実に成果へとつながるユーザー層を獲得できます。
また、ボリューム分析を軸にコンテンツ設計を行うことで、アクセスの安定化やコンバージョン率の向上にもつながります。
一方で、検索ボリュームだけを基準にした戦略はリスクもあります。
トレンド変動や競合状況を無視すると、上位表示が難しくなったり、意図しないユーザー層を集めてしまうこともあります。
重要なのは「検索数」だけでなく、「検索意図」「競合性」「コンバージョン率」などを総合的に考慮することです。
株式会社LATRUSでは、検索ボリューム分析をはじめ、SEO戦略設計から記事制作、内部対策までを一気通貫で支援しています。
キーワードの優先順位付けや、実際のコンテンツ設計に落とし込む具体的なアドバイスも提供可能です。
「どのキーワードを狙えば成果につながるかわからない」「検索数を増やしても売上が伸びない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。